現在、NHKで放送されている大河ドラマ「べらぼう」江戸の出版王と称される蔦屋重三郎(通称:蔦重)が版元・耕書堂をおこし、広重や歌麿、北斎等を世に送り出し、成功していく物語です。
花ノ井と蔦重
吉原で育った幼馴染の花ノ井(小柴風花)と蔦重(横浜流星)。花ノ井(小柴風花)は蔦重(横浜流星)が制作する細見(当時の吉原のガイドブック)の売り上げを上げるために、いわくつきの花魁・瀬川を襲名し、「五代目瀬川」となります。新花魁の襲名披露には大勢の人々が吉原を訪れ、ガイドブックである細見がとぶように売れると耳にしたからでした。少しでも蔦重役に立ちたいとの思いだったのでしょうね。にぎやかで華やかな吉原は当時の江戸の人々にとっては憧れの地であり、流行発信の街でした。 身売りをされてきた少女たちの悲惨な人生とは裏腹で、矛盾を感じずにはいられません。当時の江戸は戦もなく平和な時代が長く続き、芝居や本の出版など芸術や文化が花開いた時代でした。令和の現代と通じるものを感じます。
五代目瀬川と鳥山検校
瀬川となった花ノ井(小柴風花)は、鳥山検校(市原隼人)に見初められます。そして身請け話が持ち上がります。検校とは室町時代から続く男性盲人の組織である当道座の最高官位です。座頭(ざとう)、勾当(こうとう)、別当(べっとう)、検校(けんぎょう)等、官位が細かく分けられていました。検校はそのトップの座でした。幕府から金貸し業を認められ多額の利益を得ていました。ちなみに女性の盲人組織は瞽女(ごぜ)と言われていました。 瀬川(小柴風花)は蔦重(横浜流星)への思いを心の奥深くに秘めながら、鳥山検校(市原隼人)に身請けされていきました。自分の生きる道はこれしかないと覚悟を決めて検校の元へ行ったのでしょうね。
鳥山検校の苦悩と怒り
身請けした鳥山検校の生年など詳細は分かっていません。 五代目瀬川は瀬以(せい)と名を変え、鳥山検校の妻となります。しかし盲人である鳥山検校(市原隼人)は、瀬以(小柴風花)の秘めた思いを敏感に感じ取ります。
鳥山検校は瀬以に喜んでもらおうと、着物やかんざしなどを、好きなだけ買い与えようとしますが、瀬以(小柴風花)はこれを断り、吉原の女たちに買い与えてほしいと願うのです。鳥山検校(市原隼人)はこれを受け入れます。「どうせわしには見えぬからのう」という言葉には彼の瀬以(小柴風花)を視ることができない口惜しさともどかしさが表れていると感じます。
一方、蔦重は吉原の親方とともに検校の屋敷を訪れ、吉原を盛り上げるため、祭りを催すための許しを得に検校の屋敷を訪れます。久しぶりに会う瀬以(小柴風花)と蔦重(横浜流星)、楽しそうな話し声が聞こえてきます。「お前は吉原の者と話すときは楽しそうだな、吉原にもどりたいか」と鳥山検校(市原隼人)は瀬以(小柴風花)に詰め寄ります。
当時の江戸幕府の内情
太平の世が長く続いていた当時の江戸。町人文化が発展していく中、武士の生活は困窮しており、当道座に借金をするも返済できず娘を身売りする旗本もおりました。また出奔する者もいました。これを重く見た当時の老中、田沼意次は、当道座を解体するべく動きます。幕府は自分の家臣すら養えていないと札差(幕府の扶持米を現金に換える商人、金融業)、当道座の取り締まりを将軍家治に進言するのです。
これからの展開は?
ある夜、蔦重(横浜流星)は鳥山検校(市原隼人)から屋敷に来るよう呼び出されます。屋敷では鳥山検校が腰に刀をまとい、待ち構えます。話によっては蔦重を不義密通で斬って捨てると言い放ちます。瀬以(小柴風花)は覚悟を決め「たしかにあの男は私の光でありんした。吉原に来たのも悪いことばかりではなかったと思えた。でも今はあなたが私を吉原から救ってくれたのです。」と涙を流しながら訴えます。検校の屋敷についた蔦重でしたが、そこで目にしたのは取り締まりに来た幕府の役人の姿でした。鳥山検校と瀬以 二人は今後どうなっていくのか、、、蔦重はどう関わっていくのか、、、次の放送が待ち遠しい!! 史実を元にしたフィクションの要素もあるドラマではありますが、眼が離せません!!
《NHK大河ドラマ放送時間》 NHK総合 毎週日曜日の夜8時から NHKBS毎週日曜日の午後6時から NHKBSプレミアム4Kで午後0時15分から 《再放送》 NHK総合毎週土曜日午後1時5分から

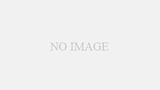
コメント