ラジオ放送が始まって今年で100年。テレビ放送がはじまって70年。僅か100年の間に、信じられないほどの進化を遂げてきました。そして人々の生活に欠かせない無二の存在となりました。
ラジオ放送開始
1925(大正14)年3月22日午前9時30分 「JOAK JOAK こちらは東京放送局であります。」と第一声が発信されました。1923年に関東大震災が発生し、正確な情報を速く、広く伝える手段としてラジオの重要性を求める声が広がり、ラジオ放送が開始されました。放送の生みの親、後藤新平が深く関わっていました。遠くで起こっていることが、瞬時に正しく伝えられることは当時の人々にとって驚きであり、また娯楽の一部として生活に欠かせないものになったと思われます。遠くの人の声が小さい箱の中から聞こえてくる!最初はさぞかし驚いたことでしょうね。
実感放送
1932(昭和7)年オリンピックのロサンゼルス大会。世界発のスポーツ生中継をするべく、3人のアナウンサーが海を渡ります。しかし放送権をめぐるトラブルから競技を実況することができず、苦肉の策で、3人は競技の内容を細かにメモし、あたかもその場にいるような雰囲気で日本に競技の様子を伝えたのです。人間の知恵って素晴らしいですね。実際の放送の録音を聴くと実況放送と何ら変わらず、その場にいるように競技の様子が伝わってきます。
戦時中の放送
正確な情報を広く速く伝えるという放送の使命が、第二次世界大戦中はねじ曲げられます。軍によって日本が不利な状況は伏せられ、あたかも日本が勝ち続けているという内容が連日放送されていったのです。その結果どうなったか、歴史をみれば明らかです。日本の「放送」にとっては暗黒の時代と言えるかも知れませんね。
テレビ放送開始
1953(昭和28)年2月1日、テレビ放送が開始されました。シャープの国産第1号のテレビの値段は175,000円(当時の公務員の初任給は高卒で5,400円)。多くの家で買える値段ではありませんでした。そこで関東地方では神社や公園にテレビが置かれ、「街頭テレビ」としてみんなはその放送を楽しんでいたのです。地方の街頭テレビがない所ではテレビを持っている近所の家に集まって放送を楽しんでいました。もちろん当時の放送は白黒でした。
テレビ放送の進化
以後、様々な番組が制作され、娯楽番組や日本全国のニュースがお茶の間に届けられるようになります。「テレビ放送は印象を残して消えていく」当時の映像は現在のような保存が効くものではありませんでした。1964年東京オリンピックではカラー放送が始まりました。当時の女子バレーボールの視聴率は66.8%。これは現在でも破られていません。1952(昭和27)大相撲中継開始。1961(昭和36)年大鵬と柏戸の対戦は52.2%。1977(昭和52)年、高校野球の中継開始。その後も多くの選手たちの名言が広く全国に伝えられてきました。「自分で自分を褒めてやりたい」女子マラソンの有森選手のこの言葉に励まされてきた方が、私を含め大勢いたと思います。
テレビ放送の役割と今後
1995(平成7)年、阪神・淡路大震災。オリックスは「がんばろう神戸」のスローガンのもと優勝し、神戸の人たちに勇気と希望を与えました。東日本大震災しかり。ただ被災地の人たちには肝心の情報が届きません。ある中学生が放送されているテレビの画面をSNSで流したそうです。今やラジオ、テレビ、インターネット等、私たちが得る情報は多方面から受け取ることができます。100年前と違って誰もが、情報を発信する立場になり、受け取る側になれます。その中で正しい情報は何なのか、しっかりと見極める目も持つことが欠かせない時代になりました。

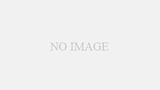
コメント